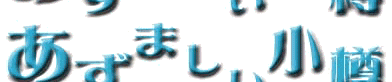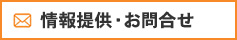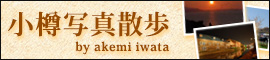9月18日(木)、小樽市立山の手小学校(花園5・草島拓也校長)では、児童に防災の重要性を伝える授業「1日防災学校」を実施した。
2018(平成30)年度から北海道と北海道教育委員会により開催され、小樽市内では小中学校で年に1校で行われ、2025(令和7)年市内の小学校で初開催された。
市総務部災害対策室の安達斉主査が講師を務め、2~6時間目で各学年ごとに防災に関するプログラムを変え、自助・共助・公助の役割と災害と防災について理解を深め、避難所設置体験を行った。全校児童349名が参加し、保護者はその様子を参観した。
草島校長は、「備えることの大切さを学び、自分の命を守る態度が大切。ひとりひとりの行動について再認識してもらいたい」と話した。
2時間目に地震を想定した避難訓練を実施。担任も児童にも知らせず、倒壊などで通れるはずの通路が塞がるなど予期せぬ事態を想定。その結果、グランドに全員が避難する時間がいつもより若干かかった。

3時間目は、1・2年生は教室でビデオを見ながら、災害が起こった時どうしたら身を守れるかなど防災について考えた。
体育館には5年生63名が集まり、これまで市内で発生した過去の災害について学んだ。2023(令和5)年9月12日の10:20~10:40に集中豪雨が発生し、市内514カ所の土砂災害警戒区域があり、山の手小学校の近くの土砂災害警戒区域を地図上で確認。
このほか、1944(昭和19)年から震度4以上の地震発生が11回、1945(昭和20)年173cmの豪雪や1996(平成8)年1月8日~9日の24時間降雪量84cmの記録を確認。
小樽でも災害被害が起き、災害の備えが不十分にならないよう、地域に起こる災害に応じて物と心の両面で災害に備えることが大切で、自分や家族を守るため、災害が起きた時は、市などからの正確な情報をもとに判断し、自分の身を守ることが重要だと学んだ。
また、避難所で使用され、小樽市でも備蓄している段ボールベッドを組み立て、完成したベッドに寝て見たり座るなどして使い勝手を確かめていた。
塚田花さんは、「避難所で使っているベッドを組み立てたり、小樽の危険な場所を教えてもらい勉強になった。1日防災学校でより知ることができた。備蓄品の準備をするように家族に話そうと思う」と話した。

4時間目は6年生が同じ内容で、5・6時間目には3・4年生にカードを用いた防災教育を行った。
今後、学校運営協議会(コミュニティスクール)を対象に防災教室を10回を予定している。
◎関連記事